
こんにちは。
『私立さつきや図書館』館長(サイト管理人)の「さつきや」です。
『限定◯点』
『最高品質!』
『当店だけの特別カラー』
そんな言葉を、作品の紹介やSNSの投稿で何気なく使っていませんか?
実はこうした表現は、場合によって「景品表示法(けいひんひょうじほう)」という法律に触れてしまう可能性もあります。
景品表示法は、企業だけでなく、ハンドメイド作家のように個人で販売活動をしている人も対象になります。
結論から言うと、ハンドメイド販売で嘘をつかないこと、ズルをしないこと。
この2点を守っていれば、そんなに心配する必要はありません。
この記事では、作家さんが知っておきたい景品表示法の基本と、うっかり行ってしまいそうなNGポイントをわかりやすく紹介します。
※ 冒頭のフレーズについては後半の『Q&Aコーナー』で解説しています▼
本記事内で景品表示法についてすべて網羅できているわけではありません。
また、世の中に合わせて規制も変化しています。
詳しい情報は専門書籍や消費者庁の情報を参考にしてください。
【こちらの記事は2025年10月20日現在の情報をもとに執筆しております。】
景品表示法の基本

まずは、景品表示法について簡単に解説します。
この記事では、ハンドメイド作家さんに関係のある部分を中心に、できるだけやさしく紹介していきます。
実際のルールはもっと細かく決められていますが、まずは全体像をつかむつもりで読んでみてください。
景品表示法の概要

景品表示法の呼称
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
略称として「景品表示法」または「景表法」とも呼ばれていますが、この記事内ではもっとも一般的な「景品表示法」の呼称を使用します。
景品表示法の役割

景品表示法は簡単に言うと「消費者をだますような広告・キャンペーンを禁止する法律」です。
これらのような行為で消費者が買い物をする際に、冷静な判断をできなくなるのを防ぐ目的があります。
また、そうした不正行為をしない誠実な事業者を守ることにもなります。
継続的に販売行為を行っている場合、たとえ個人であっても事業者としてみなされます。
そのため、販売活動を行うハンドメイド作家さんは景品表示法の規制の対象となります。
「表示」と「景品」

景品表示法は、大きく分けて2つのルールを定めています。
「表示」とは文章に限ったものではありません。
ハンドメイドマルシェなどでの口頭での説明やPRなども含まれます。
ここからは、表示・景品について順に説明します。
景品表示法における「表示」とは?

まずは「表示」について解説します。
景品表示法の「表示」とは、消費者に商品やサービスを選んでもらうために行う、すべてのアピールを指します。
販売ページに書かれた説明文やSNSの投稿だけでなく、タグ・チラシ・パッケージ・さらにはイベントでの口頭での案内までが含まれます。
これらすべてが「表示」に含まれます。
【表示の責任者は誰?】
「表示」は、事業者(=販売者)が自分の提供する商品やサービスについて行うものであれば対象になります。
対象となるのは、minneやCreemaなどのプラットフォームそのものではなく、作品を出品・販売しているハンドメイド作家さん個人です。
販売ページの内容や宣伝文などについては、作家自身が「表示の主体」として責任を負う立場になります。
※ プラットフォーム側が自社名義で広告・販売したり、違反を把握して助長したような特段の事情がある場合は、別途責任が問われることもあります。
景品表示法ではさまざまな表示に関するルールが定められています。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- ステルスマーケティング
1.優良誤認表示

作品の品質・性能・効果などを、実際よりも優れているように見せる表現です。
また、根拠のない断定的な言葉も優良誤認とみなされる可能性があります。
「しっかりした作り」「丁寧に仕上げました」など、事実に即したやわらかい表現にすると安心です。
「他の作家よりも高品質です」など比較を示す表現も、根拠がなければ避けた方が安全です。
2.有利誤認表示

価格や条件を実際よりも有利(お得)に見せる表現です。
たとえば「通常3,000円→今だけ2,000円」と書いているのに、実際には3,000円で販売した実績がない場合は有利誤認になります。
「期間限定セール」と書きながら同じ価格を継続して販売する場合も、誤認を与えるおそれがあります。
「イベント限定価格」「在庫処分のため値下げ」など、事実をそのまま書くことが一番安全です。
数量や期間を限定して特別価格をPRする場合は、宣言した内容を必ず守りましょう。
3.ステルスマーケティング(ステマ)

景品表示法では、広告であるのに広告とわからない形で宣伝する行為も禁止されています。
事業者(この場合は作家自身)が宣伝を行うときは、それが「宣伝」であると消費者にわかるようにする必要があります。
こうした行為は消費者を誤解させるおそれがあります。
作品や金品を提供してレビューしてもらう場合は、「提供」や「PR」などを明示すれば問題ありません。
また、文言を指定したり、良いレビューを強制しなければ「レビュー評価も書いてくださいね」とお願いするのは違反行為ではありません。
景品表示法における「景品」とは?

次に「景品」についての解説です。
景品とは、作品の購入や来店などのきっかけを作るために、事業者があわせて提供する「特典」や「おまけ」のことを指します。
プレゼント、ノベルティ、割引券、無料サービスなど、購入者にとって追加のメリットとなるものは、すべて景品に含まれます。
逆に、次のようなものは原則として景品には当たりません。
景品の判断基準

景品とみなすかどうかのポイントは次の二つです。
「誰でも応募できる」オープン懸賞(購入不要)は、基本的に景品規制の対象外です。
ただし、来店すると当選確率が上がる・クイズのヒントがもらえるなど、実質的に取引を促すような仕組みになっている場合は、景品とみなされることがあります。
景品表示法では景品の金額に上限がある

景品表示法では、商品の購入やサービスの利用をきっかけにプレゼントを配るとき、景品(おまけや特典)の金額に上限が決められています。
これは、過度に豪華な景品でお客さまの購買判断を誤らせたり、競争を不公正にすることを防ぐためのルールです。
ハンドメイド作家さんの場合も、「購入者にノベルティをプレゼント」「フォロー&いいねで抽選プレゼント」などを行うときは、この上限に注意が必要です。
景品の種類と上限

景品の上限は、どのタイプの企画かによって変わります。ハンドメイド販売でよく出てくるのは次の三つです。
1.総付景品(そうづけけいひん)

購入者や来店者「全員にもれなく」配る景品です。
例:購入者全員にポストカードプレゼント など
2.一般懸賞

購入者などを対象に、抽選やゲーム・クイズで当選者にだけ渡す懸賞企画です。
例:購入者の中から抽選で1名にトートバッグをプレゼント など
3.共同懸賞

商店街やイベント主催者など、複数の事業者が「共同で」行う懸賞です。
例:ハンドメイドマルシェ全体で行われる抽選くじで会場内で利用できる買い物券 など
景品に「なるもの」「ならないもの」をおさらい

どんなものが景品にあたるのか、改めて整理してみましょう。
景品に該当しても、金額の上限が適用されない例外もあるため注意が必要です。
「無料メンテナンス」や「名入れサービス」などは、普段有料で提供しているものを「特典として無料にする」場合は景品にあたります。
ただし、最初から全員に無料で行っているサービスや、品質保証の範囲に含まれるものは景品ではありません。
【注意したいケース】
ハンドメイド販売での景品表示法Q&A

ここからは、ハンドメイド作家さんが景品表示法に関して感じる具体的な疑問をQ&A形式でご紹介します。
- Q1ハンドメイド作家も法律の対象になるの?
- A
なります。
継続して販売を行っている場合は「事業者」とみなされるため、景品表示法の対象です。
販売数が少なくても、営利目的で繰り返し販売していれば該当します。
- Q2「最高品質」って書いたらダメ?
- A
「最高」「唯一」「完璧」などの最上級表現は、客観的な根拠がない限り避けましょう。
主観的な表現にするか、「高品質を目指して制作しています」「丁寧に仕上げました」といった言い回しにすると安全です。
- Q3「限定◯点」と書いたらダメ?
- A
実際に数量を限定している場合は問題ありません。
ただし、在庫を追加したり、同じ作品を再販したりする場合は、その理由を明示する必要があります。
例:
「再販リクエスト多数につき再制作しました」
「予定外に同じ材料が再入荷したため販売を再開しました」など
最初から「限定」と書いておきながら、理由を示さずに数を増やしたり再販を繰り返したりすると、有利誤認表示と判断されるおそれがあります。
- Q4「当店だけの特別カラー」と書いたらダメ?
- A
本当に自分だけが販売しているオリジナル塗装や限定色なら問題ありません。
ただし、他の作家やメーカーでも同じ素材・カラーが購入できる場合は、「当店だけ」と言い切ると誤認を与える可能性があります。
「当店こだわりの色合わせ」「当店で厳選したおすすめカラー」など、事実に即した表現にしましょう。
- Q5当初の予定よりも「期間限定セール」を延長してもいい?
- A
実際に期間を延長する場合は、「好評につき期間延長しました」など理由を明記すれば問題ありません。
ただし、何度も「数量限定」「期間限定」を繰り返すと、有利誤認表示とみなされることがあります。
- Q6購入してくれたお客さまにオマケを付けても問題ない?
- A
取引金額1,000円未満なら200円まで、1,000円以上なら20%までが上限です。
500円の作品に100円程度のポストカードを付けるなど、常識的な範囲であれば問題ありません。
なお、最初から全員に無料で付けているラッピングやメッセージカードなどは、景品ではなく通常のサービスとみなされます。
- Q7SNSでフォロワーにプレゼント企画をしたいけど景品になる?
- A
購入不要の「誰でも応募できる」懸賞企画(オープン懸賞)は、基本的に景品表示法の対象外です。
SNSアカウントをフォローする・コメントを書く程度の条件なら、オープン懸賞の範囲内とみなされます。
ただし、「作品を買った人限定」「投稿した人だけ当選チャンス」などの条件をつけると景品扱いになります。
また、懸賞企画内で過度な販促PRを行い、実質的に購入を誘導していると判断される場合も景品に該当します。
※ 景品扱いでプレゼント企画をする場合は、景品の上限金額(総付・懸賞の上限)を守る必要があります。
- Q8ハンドメイドマルシェで途中から値下げをしたい。
値段を書き換えてPOPを出すのは違反? - A
イベント期間中に価格を変更すること自体は問題ありません。
ただし、「元値」を表示して値下げをアピールする場合は、同じイベント内で実際にその価格で販売していた実績がある必要があります。景品表示法では「二重価格表示」についての規制も定められています。
しかし、1〜2日程度のマルシェなど、販売期間が短い場合は「通常価格」として認められる期間がないため、二重価格表示の規制対象にはなりにくいとされています。「イベント限定価格」「最終日特別価格」「売り切り特別価格」など、理由を明示した表現にすると、より誤解を防げます。
- Q9ハンドメイドマルシェで主催者がくじを開催。買い物券プレゼントは問題ない?
- A
出展者が多数参加する合同イベントで、主催者がくじを行う場合は「共同懸賞」にあたります。
景品の上限は、1等の最高額が30万円まで、総額はそのイベント期間中の売上予定額の3%以内です。
主催者がその金額の範囲内で管理していれば問題ありません。
※ 出展者個人が自分のブースで独自にくじを行う場合は「一般懸賞」となり、最高10万円・総額2%以内が上限です。
景品表示法を違反したらどうなる?

景品表示法は、主に消費者を守るために行政が事業者を監督・指導する法律です。
違反が確認された場合、消費者庁や都道府県が措置命令・課徴金などの行政処分を行うことがあります。
これらは、再発防止を目的としたもので、刑事罰ではありません。
ただし、個人で活動するハンドメイド作家さんが処分を受けるケースは非常にまれです。
よほど悪質な虚偽表示や高額な景品キャンペーンを繰り返すような行為でなければ、行政指導の対象になることはほとんどありません。
とはいえ、違反しても良いというわけではありません。
誤解を与えない、誠実な表示をして、クリーンな販売活動を心がけましょう。
参考サイト・書籍
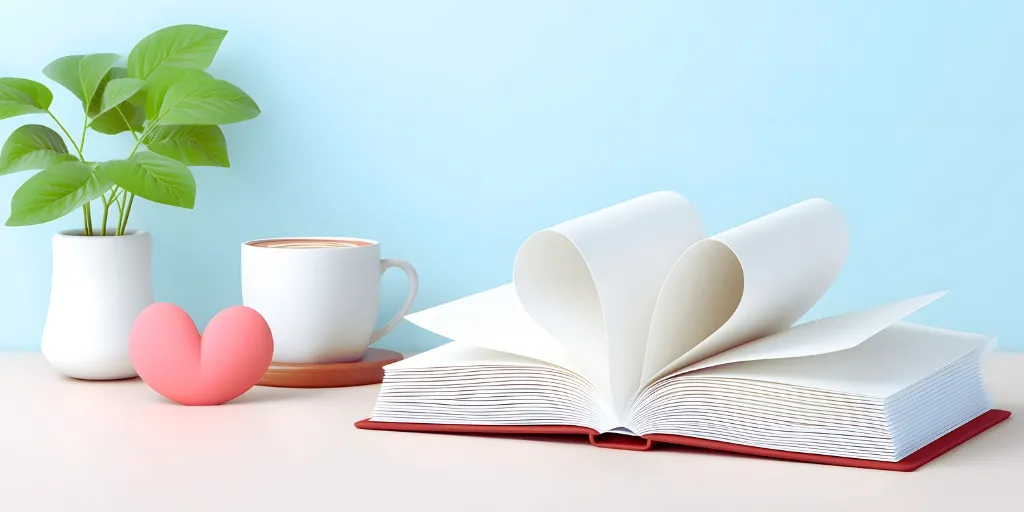
これまで解説した通り、景品表示法は、誠実に販売活動をしていれば大きな問題になることはありません。
とはいえ、景品の金額や表示内容など、知らないうちにルールに触れてしまうこともあります。
安心して活動を続けるためにも、基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
ここでは、ハンドメイド作家さんにも役立つ参考サイトと書籍を紹介します。
参考サイト:消費者庁公式サイト
景品表示法を管理する消費者庁の公式サイト内には、景品表示法に関する情報をまとめたページがあります。
見やすい、わかりやすいとは言えませんが、最初は「景品表示法のパンフレット(PDF)」から目を通すのがおすすめです。
▼外部リンク:消費者庁公式サイト内『景品表示法』▼
参考書籍:『景品表示法がよくわかる本』
『図解ポケット 最新の改正に対応!景品表示法がよくわかる本』
著者:嶋村直登 出版社:秀和システム 発行:2025年7月5日
景品表示法の基本をやさしく解説した入門書です。
説明が丁寧で、法律に苦手意識がある方でも理解しやすい内容になっています。
専門書としては基本中の基本の内容なのだと思いますが、必要な情報はしっかり網羅されています。
ハンドメイド作家さんがまず知っておきたい最低限の知識を身につけるには、この一冊で十分ではないでしょうか。
専門的な本はあまり分厚いと読む前から気が重くなってしまいますが、この本は140ページほどで気軽に読み進められるボリューム感でした。
挿絵は少なめですが、一つ一つの項目の文字数もそんなに多くなく、文字サイズも小さ過ぎずちょうど良いので読みやすかったです。
言葉遣いも難しくないので、まず全体像をつかむには最適な難易度の本だと思います。
まとめ
今回は、ハンドメイド作家さん向けに景品表示法の基本と、販売活動でありがちな身近な疑問をまとめました。
景品表示法は難しく感じるかもしれませんが、要は「嘘をつかないこと」「ズルをしないこと」。
この2点を守っていれば、過度に心配する必要はありません。
ただし、ハンドメイド販売を継続して行う以上、事業者としての責任があることも事実。
一度は景品表示法の基本を確認し、正しい知識を身につけておくことをおすすめします。

今回もお読みいただき、ありがとうございました

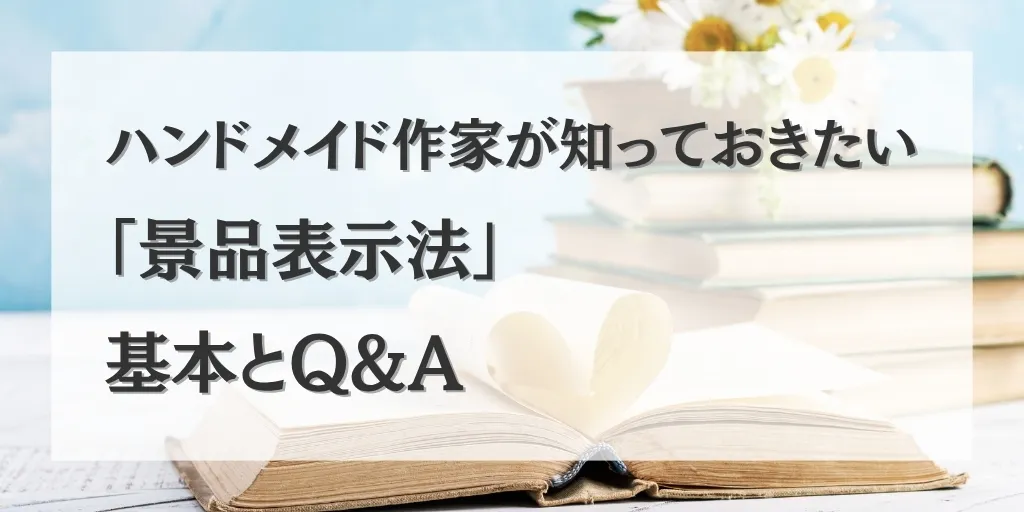

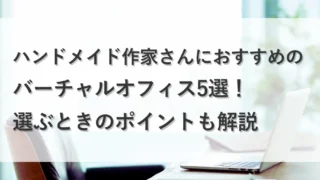
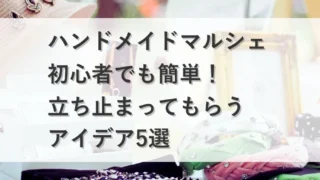
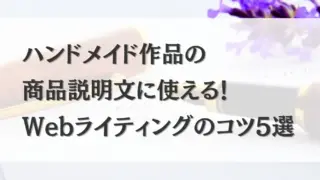
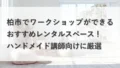
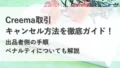
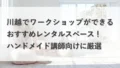
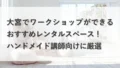
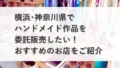
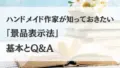
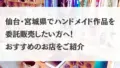
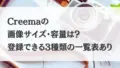
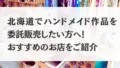
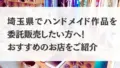
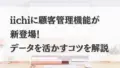
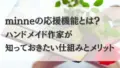
コメント