販売活動をしているうえで、実は木津かづにトラブルが発生しているかもしれません。
今回は、ハンドメイド販売におけるサイレントクレーマーについて解説します。
「サイレントクレーマー」という言葉をご存じでしょうか?
一見、怖そうな名前ですが、実は誰にでも心当たりのある身近な問題であることに気が付くでしょう。
この記事ではといったことをわかりやすく解説します。
サイレントクレーマーとは?

まず、サイレントクレーマーとは何か、概要を説明します。
ハンドメイド作品を販売していると、時にはトラブルが発生することもあります。
その際には、以下のような対応をとることで解決に向かうことができます。
minneやCreemaなどの販売サイトを利用していれば、運営に相談することも可能です。
しかし、トラブルは必ずしもクレームとして表面化するわけではありません。
不満を持って黙って立ち去るサイレントクレーマー

「クレーマー」という言葉は、多くの人にとって馴染みのあるものではないでしょうか?
簡単に言えば、「売り手に苦情を言う買い手」のことを指します。
理由や動機はさまざまですが、共通するのは「不満を言葉にして伝える」点です。
では、「サイレントクレーマー」とは何でしょうか?
クレーマーが不満を伝える一方、サイレントクレーマーは、不満があっても、それを売り手に伝えない買い手のことです。
行動としては以下のような特徴があります。
場合によっては、周囲の人に不満をこぼし、悪い評判を広めてしまうこともあります。

あそこで買い物をするのはやめた方がいいよ
こうしたサイレントクレーマーの存在は、表面化することがほとんどなく、売り手が気づくのは難しいのです。
しかし、不満を感じたお客様のうち、クレームとして伝える方は1割にも満たないとも言われています。
残りの9割以上は、何も言わずに静かに離れていってしまうサイレントクレーマーとなるのです。
サイレントクレーマーは「普通の人たち」

ここまで読んで、

サイレントクレーマーって陰湿でイヤな人なの?
と感じたかもしれません。
でも、ちょっと考えてみてください。
何か買い物をしたり、お店でサービスを受けたとき、
「ちょっとやだな…」
「期待したのと違うな…」
と感じたことはありませんか?
そのたびに、お店にクレームを入れていましたか?
そんなに特別な行動をとっているでしょうか?
サイレントクレーマーとは特別な存在ではなく、ごく普通の人たちなのです。
さつきやがサイレントクレーマーになった話

これはサイト運営者「さつきや」の体験談です。
実は過去にハンドメイド作品を購入した際、サイレントクレーマーになった経験があります。
ある作家さんから作品を購入したのですが、発送予定日を過ぎても発送通知が届かず、作家さんからの連絡もありませんでした。
不安になって問い合わせをしたところ、メッセージでお返事をいただきました。
そのメッセージの冒頭が「すいません」という言葉だったのです。
今回のように、明らかに作家さん側に非があった場合、ビジネスとしての謝罪の言葉はやはり「申し訳ありません」です。
少なくとも、「すいません」ではなく「すみません」と書くべきだとわたしは思いました。
大変失礼で申し訳ないのですが、「ちょっと常識に欠ける人なのかな」と感じてしまったのです。
とはいえ、それをメッセージで指摘することもなく、わたしは黙ってそのまま取引を終えました。
その後、遅れながらも品物は届きましたが、レビューを書くこともなく、リピート購入もしていません。
販売者側の作家さんは

発送が遅くなって、不満を持たれたかな…
くらいには感じたかもしれません。
ですが、わたしが本当に気になったのは、言葉遣いや、予定通りに取引ができなかった際の対応の仕方でした。
それを作家さんに伝えることもなく、わたしは静かに離れました。
おそらくリピートすることもないと思います。
作家さんが本当の理由に気づくことは、おそらくないでしょう。
以上が、わたし自身がサイレントクレーマーになった実体験です。
サイレントクレーマーの何が怖いか

ハンドメイド作家さんに限らず、一流企業でもサイレントクレーマーは軽視できない存在 です。
先に説明したとおり、サイレントクレーマーは不満を持っても直接苦情を伝えてきません。
そのため、表立ったトラブルは起きていないように見えます。
サイレントクレーマーの何がそんなに怖いのでしょうか?
その理由として、次の3つが挙げられます。
- 売り手はサイレントクレーマーの存在に気づけない
- 改善点を知ることができない
- 未来のお客様も失うリスクがある
1.売り手はサイレントクレーマーの存在に気づけない

サイレントクレーマーは、売り手に直接苦情を言いません。
ハンドメイド作家さんにとっては、何の問題もなく取引が終わったように感じているはずです。
レビュー評価やリピート購入がなかったとしても、「以前一度購入してくれたお客様」として、特に違和感もないかもしれません。
しかし、
作家さんの見えないところで「もうこの人からは買わない」と判断し、周囲にも「この人の作品はやめておいた方がいい」と伝えているかもしれません。
まさに“見えないトラブル”です。
どこでサイレントクレーマーが発生したのか、作家側には気づくすべもありません。
見えないところで評価が下がり、悪い口コミが広がる。
それがサイレントクレーマーの怖さです。
もちろん、レビュー評価をしないお客さま・リピート購入をしないお客さまのすべてがサイレントクレーマーというわけではありません。
ですが、作家さんからはその違いを見分けることができません。
疑い始めるとキリがなく、考えたところで本当のところは分からないのです。
だからこそ、ハンドメイド作家にとって、サイレントクレーマーという存在はとても怖いのです。
2.改善点を知ることができない

クレームがあった時、ハンドメイド作家さんは落ち込んだり、自信を失ったりすることもあるでしょう。

もう販売活動をやめたい…
と感じてしまう時もあるかもしれません。
クレームの中には、お客様の思い違いや、時には理不尽な理由が含まれている場合もあります。
それでも、クレームが届いたということは、不満の原因がこちらに伝わっているということです。
「何に不満を感じたのか」「どこを改善すべきか」を知るチャンスでもあります。
同じトラブルを繰り返さないための対策を立てることができるのです。
一方、サイレントクレーマーの場合は、何も言わずにそのまま離れてしまいます。

一言伝えてくれれば、すぐに改善できたことなのに…
そう思うような理由もあるかもしれません。
けれど、教えてもらえないのです。
「ここを直してほしい」と指摘してくれるのは、期待を込めた親切・誠実の表れであることもあります。
そうした声が届けられることもなく、ただ黙って見限られてしまう
それはとても辛く悲しく、そして怖いことですよね。
2‐1.レビュー評価では改善点に気づけない?

通販サイトでは、レビュー評価を通じて、売り手側がさまざまな気づきを得ることもあります。
ハンドメイド販売の場合はどうでしょうか。
個人的な考えでは、
ハンドメイド販売の場合、そのレビューの役割がやや弱い傾向があると感じています。
たとえば、minneやCreemaなどのハンドメイド販売サイトでは、よほどのことがない限り高評価がつくことが多く、ネガティブな感想が表に出にくい空気感があります。
【一般的な通販サイト】
購入者が気軽に辛口評価・不満点を投稿する場面も
⇩
理不尽なこともあるが、改善点にも気づきやすい
【ハンドメイド販売サイト】
作家と購入者の距離が比較的近く、
「ネガティブことは書きにくい」雰囲気
⇩
嫌がらせなどで傷つくことは少ないが、お客様の本音が聞けないことも…
もちろん、正直な意見を書いてくださるお客様もいます。
また、ポジティブな感想がすべて建て前といっているわけでもありません。
けれど、
ハンドメイド販売においてはレビュー評価だけでは本当の改善点に気づきにくい構造があるという点がある。
そのことは、ハンドメイド作家さんが意識しておくべきことだと、わたしは思います。
3.未来のお客様も失うリスクがある

サイレントクレーマーは時に、自分の不満を他の人に伝えることがあります。
それらは、身近な人との気軽な愚痴や世間話、善意の情報共有として行われます。
中には、意図的にそのハンドメイド作家さんの評判を下げようとする意地悪な気持ちが含まれている場合もあるかもしれません。
そうした感想や口コミを聞いた人の多くは、実際にその作家さんから購入する前に

この作家さんから買うのはやめよう
そう判断するでしょう。
それはつまり、
本来ならご縁があったかもしれない未来のお客さまが、直接関わる前に離れてしまうということです。
知らぬ間に、販売のチャンスを失っているかもしれない。
これこそが、サイレントクレーマーの最も恐ろしく、深刻な特徴と言えるでしょう。
サイレントクレーマーを防ぐには
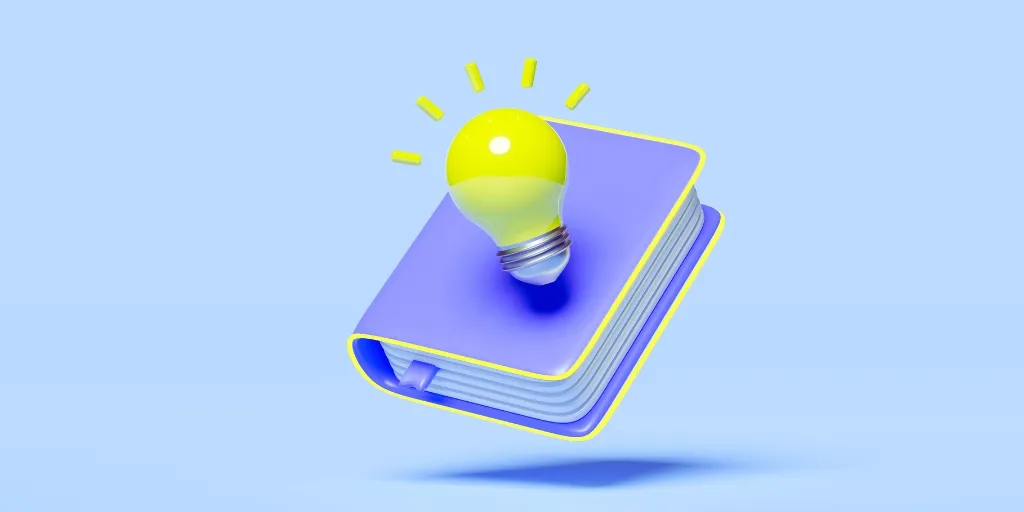
サイレントクレーマーの何が怖いのか、ここまででお伝えしてきました。
では、そうしたサイレントクレーマーが発生するのを防ぐ方法はあるのでしょうか。
結論から言うと、完全にゼロにすることは難しいと思います。
そもそも、サイレントクレーマーの存在に気づくこと自体が難しいのです。
お客様が黙って去っていく以上、「発生したかどうか」すら判断できないのが実情です。
だからこそ、完全になくすのは現実的ではないと考えた方が良いでしょう。
ですが、できる限り発生を減らすための対策、予防は可能です。
ハンドメイド販売でのトラブルを未然に防ぐという意味でも、サイレントクレーマー対策は意識しておきたいところです。
ここでは、予防のために意識したい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1.品質を高める

まず何よりも、不満を持たれないように努力をすることが大切です。
とにかく、自分自身のハンドメイド作家としての質を高めることを意識しましょう。
これはサイレントクレーマー対策としてだけでなく、常に意識しておきたい姿勢でもあります。
「品質を高める」と一言で言っても、その対象はさまざまです。
品質を高める‐作品クオリティ
ものづくりのスキルアップを積極的に心がけましょう。
また、作品は耐久性にも気を配る必要があります。
たとえば「身につけた途端に壊れてしまった…」となれば、お客様は当然がっかりしてしまいます。
品質を高める‐作品ページの画像や文章
作品の魅力をしっかりと伝えると同時に、誤解を与えず正確に伝えることも大切です。
「思っていたものと違った」
という不満は、特にネット通販では起こりやすいトラブルの一つです。
品質を高める‐販売時、取引中の対応
今一度、見直してみましょう。
お客様が「雑に扱われている」と感じてしまえば、それだけで不満につながります。
しっかりと敬語を使い、丁寧に「あなたとのご縁を大切にしています」という気持ちで接することが基本です。
もちろん、丁寧さは必要ですが、あまりに形式的・事務的すぎると、かえってそっけない印象を与えてしまうこともあります。
お客様によって求める距離感は異なるので難しいですが、礼儀正しくあることは最低限のマナーだとわたしは思います。
そのうえで、「気軽にコミュニケーションもできますよ」という親しみやすい姿勢を見せられたら理想的です。
お客様にとって心地よい距離感を、自分が決めるのではなく、相手に任せられる作家でありたい。
これは、売り手であるわたし自身の目標でもあります。
ポイント2.お客様を不安にさせない取引をする

お客様とのやり取りの中で、不安にさせないことはとても重要です。

この作家さん、大丈夫かな…
わずかな不安も、放置すればどんどん大きくなり、やがて不満へと変わってしまいます。
先に述べたように、正確な説明で誤解を防ぐこと、取引中にもこまやかな案内をして安心感を与えることが大切です。
もちろん、取引のすべてに丁寧に対応できれば理想ですが、現実的には難しい場面もあるでしょう。
例:レビュー返信をしないハンドメイド作家さん
たとえば、「レビュー評価への返信はしない」という方針の作家さんもいらっしゃるかと思います。
取引件数が多くて返信が追いつかず、一律で返信していない方もいるでしょう。
しかし、お客様によっては「返信するのが普通」という考えを持っている場合もあります。
そのような方にとっては

せっかくレビューを書いたのに無視された。失礼な人だな…
こんなマイナスの印象を持たれてしまうかもしれません。
こうした小さな認識のすれ違いを放置すると、見えないトラブルにつながってしまうこともあるのです。
この場合、正確な説明で誤解を防ぐ手立てとして「しないこと」をあらかじめ明記しておくのも一つの方法です。
たとえば、
レビュー評価への返信はしておりませんが、必ずありがたく読ませていただいています。
このような一文を、作品ページや取引メッセージに添えておくだけで、認識のズレを防ぐことができます。
ちょっとした先のことを明確に伝えることで、お客さまに安心感を与え、誤解を生む可能性も減らすことが可能です。
もちろん、完璧な効果があるわけではありませんが、少しでも見えないトラブルを減らす助けにはなるでしょう。
不安を与えない取引の重要性については、別の記事でも詳しく解説しています。
ポイント3.自分からお客様を好きになる
3つ目のポイントは、とてもシンプルです。
お客様を、まずは自分から好きになりましょう。
売り手であるハンドメイド作家も、もちろん人間です。

このお客様は問題なく取引してくれるだろうか…

理不尽なクレームをつけてきたりしないかな…?
そんなふうに、多少の緊張や警戒心を持つこともあるでしょう。
イベントでの対面時はもちろん、ネット販売でのメッセージのやり取りでも、そうした気持ちは意外と相手に伝わるものです。
こちらが相手を警戒すれば、相手もこちらを警戒します。
そして、人は自分に好意を示してくれる相手に対して、好意で返そうとする傾向があります。
こちらから好意を示すことで、お客様も少しずつ心を開いてくださいます。
もちろん、「お客様を好きになる」と言っても、いきなり「あなたが好きです」と告白するなんて意味ではありません。
丁寧な言葉でのやりとり、感謝の気持ちを忘れない、お礼をしっかり伝える。
そういった誠実な対応すべてが、好意を示す行動になります。
つまり、「あなたとのご縁を大切に思っています」と、態度で伝えることです。
距離感を近くして馴れ馴れしくするという意味ではありません。
やりとりを最小限にとどめて、効率よく買い物をしたいというお客様もいらっしゃいます。
一方で、作家さんとのコミュニケーションを楽しみにしている方も。
一人一人のお客様に安心して気持ちよく買い物をしていただけるような、取引ごとにちょうどよい距離感を築いていきたいものです。
すべての取引で100%、お客様と信頼関係が築けるわけではありません。
でも、そうなれるように努力していきましょう。
サイレントクレーマーにさせない一番の近道は、「この人なら、ちょっとした気になることも伝えて大丈夫」と思ってもらえるような信頼関係を築くことかもしれません。
参考書籍の紹介
サイレントクレーマーについて、より深く知りたい方におすすめの参考書を紹介します。
『沈黙のサイレントクレーマー 顧客満足度100%のツボ』
(宮﨑聡子著・2008年出版・青春出版社)
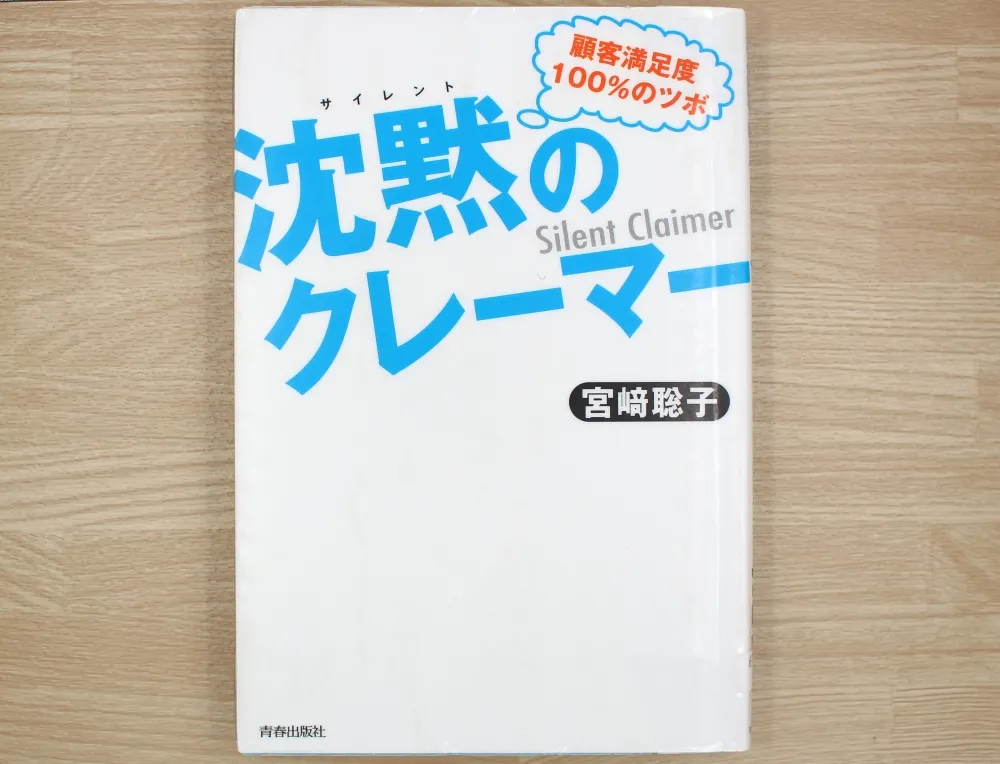
サイレントクレーマーとなるお客さま心理より理解を深めることで、販売者としてのクオリティ向上にもつながるはずです。
まとめ
今回の記事では、ハンドメイド販売における「サイレントクレーマー」について解説しました。
不満を持ったお客様の多くは、クレームとして表面化せずに静かに離れていくものだという前提を持ち、日頃から予防の意識を持って取り組んでいくことが大切です。
わたし自身も、販売活動の中で、常に気をつけていきたいです。
販売活動をされている全国のハンドメイド作家の皆さま、お互いにこれからも頑張っていきましょう。

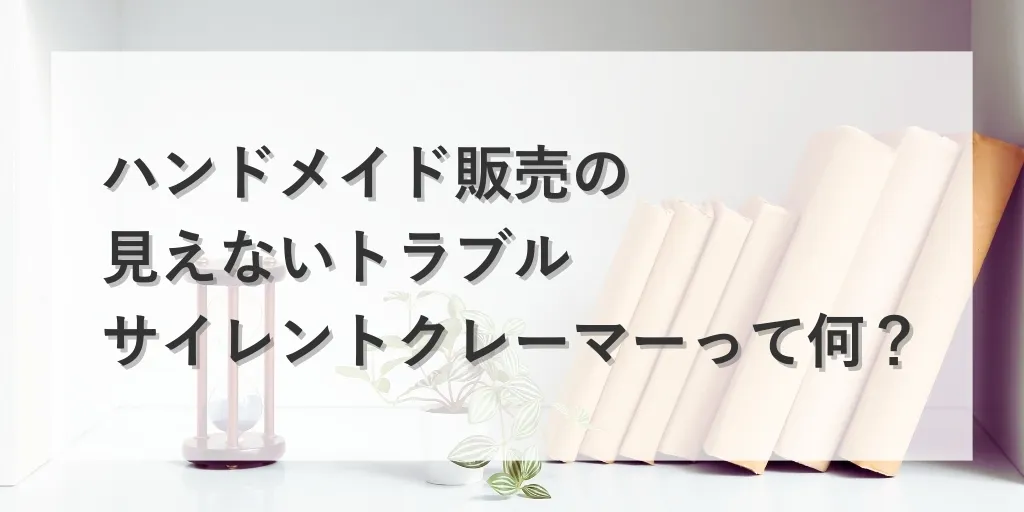
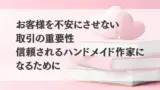

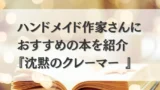
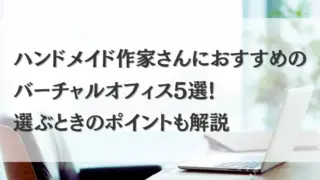
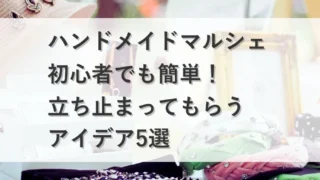
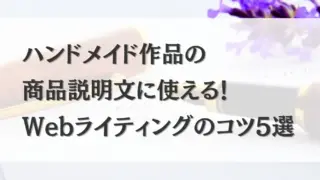
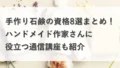
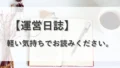
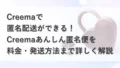
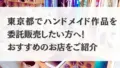
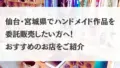
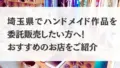
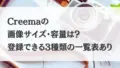
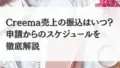
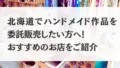
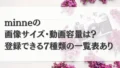
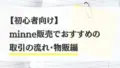
コメント
お邪魔します
趣味のハンドメイドから販売する側になるために必要な事とか、知りたかった事とか丁寧に書かれててどの記事も勉強になります
自分はまだまだそんな気がありませんがいつか(定年後とか)できたらなぁ…はあるので
なるほどなぁと思うばかり✨
また遊びに来ますね
miyaさん!!✨
コメントありがとうございます(>人<)
とても励みになります
少しでもご参考になる記事を書けるようにこれからも頑張ります!
ぜひまたお待ちしております